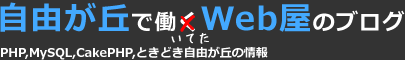三渓園で『三渓そば』を食べてみた
三渓園で『三渓そば』を食べてみた
三渓園の名物『三渓そば』を食べてきました。
詳細は以下から。
三渓園とは

三溪園(さんけいえん)とは、横浜市中区にある日本庭園です。
最寄り駅は京浜東北・根岸線の根岸駅や山手駅。
駅からは距離があり、根岸駅や桜木町駅、横浜駅からはバスが出ています。
以下、Wikipediaから抜粋。
17.5haの敷地に17棟の日本建築が配置されている。実業家で茶人の原富太郎によって作られた。名称の三溪園は原の号である三溪から。2006年11月17日に国の名勝に指定された。公式サイトでは旧字体の「溪」を使うが、横浜市公式サイトなど新字体を使って三渓園と表記することも多い。
三溪そば

三渓園内の正門を入って左側に少し歩いた『待春軒』という食事処。

メニューはこの様な感じ。
三渓そばの説明には
『三渓園の創設者、原三渓が考案したおそばです』
と書いてあります。
名前は『そば』ですが、油で軽く炒めた温かい細いうどんであり、蕎麦では無い様です。

三渓そばが運ばれてきました、どーん!
右上に写っているのは緑茶ではなく昆布茶。

上に乗っている具は刻んだハムに錦糸卵、インゲン。
つゆは入っておらず、筍や椎茸などを甘辛く煮詰めた餡がかかっています。

面は細く白いうどん。
油で炒めているとの事ですが、そこまでベトついてはいません。

味の方は『汁無し五目うどん』もしくは『和風ジャージャー麺』といった感じ。
汁がまったく入っていないので、よくかき混ぜてから食べないと味に偏りが出てしまうかも。
味・食感ともに楽しめ、美味しく頂きました♪
三渓園の景色

蓮の花が見頃でしたが、昼過ぎに訪れたので既に花は閉じてました。
この次期は『早朝観蓮会』という行事が行われている様です。

『鶴翔閣(かくしょうかく)』。
三渓が住まいとして建てた、延床面積950㎡の規模を誇る建築。

『臨春閣(りんしゅんかく)』。
紀州徳川家初代藩主の頼宣が和歌山・紀ノ川沿いに建てた数奇屋風書院造りの別荘建築。
重要文化財に指定されている建築物。

園内西側の景色。
当日は30度超えの真夏日でしたが、木陰は涼しい風が吹き、過ごしやすかったです。

『旧天瑞寺寿塔覆堂(きゅうてんずいじ じゅとうおおいどう)』。
豊臣秀吉が京都・大徳寺に母の長寿祈願のために立てさせた寿塔(じゅとう・生前墓)を納めるための建築。
重要文化財に指定されている建築物。

『亭榭(ていしゃ)』。
三渓園のパンフレットには『亭樹』と書いてありますが正しくは『亭榭』の様です。
『榭』とは『屋根のある台』という意味を持ち、亭榭とは『あずまや』や『見晴らし台』の事。

『月華殿(げっかでん)』。
京都・伏見城にあった、大名来城の際の控え所として使われたといわれる建物。
重要文化財に指定されている建築物。

『天授院(てんじゅいん)』。
鎌倉・建長寺近くの心平寺跡にあった禅宗様の地蔵堂の建物。
重要文化財に指定されている建築物。

『聴秋閣(ちょうしゅうかく)』。
京都・二条城内にあったといわれる、徳川家光・春日局ゆかりの楼閣建築。
重要文化財に指定されている建築物。

『旧燈明寺三重塔(きゅうとうみょうじ さんじゅうのとう)』。
京都・木津川市の燈明寺(廃寺)にあった建物。
現在、関東地方にある木造の塔では最古のもの。
重要文化財に指定されている建築物。

『旧矢箆原家住宅(きゅうやのはらけじゅうたく)』。
白川郷にあった合掌造りの建物。
園内にある歴史的建造物の中で唯一内部を見学できる建物。
重要文化財に指定されている建築物。

合掌造りの屋根。
どこからか飛んできた種が目を出しています。